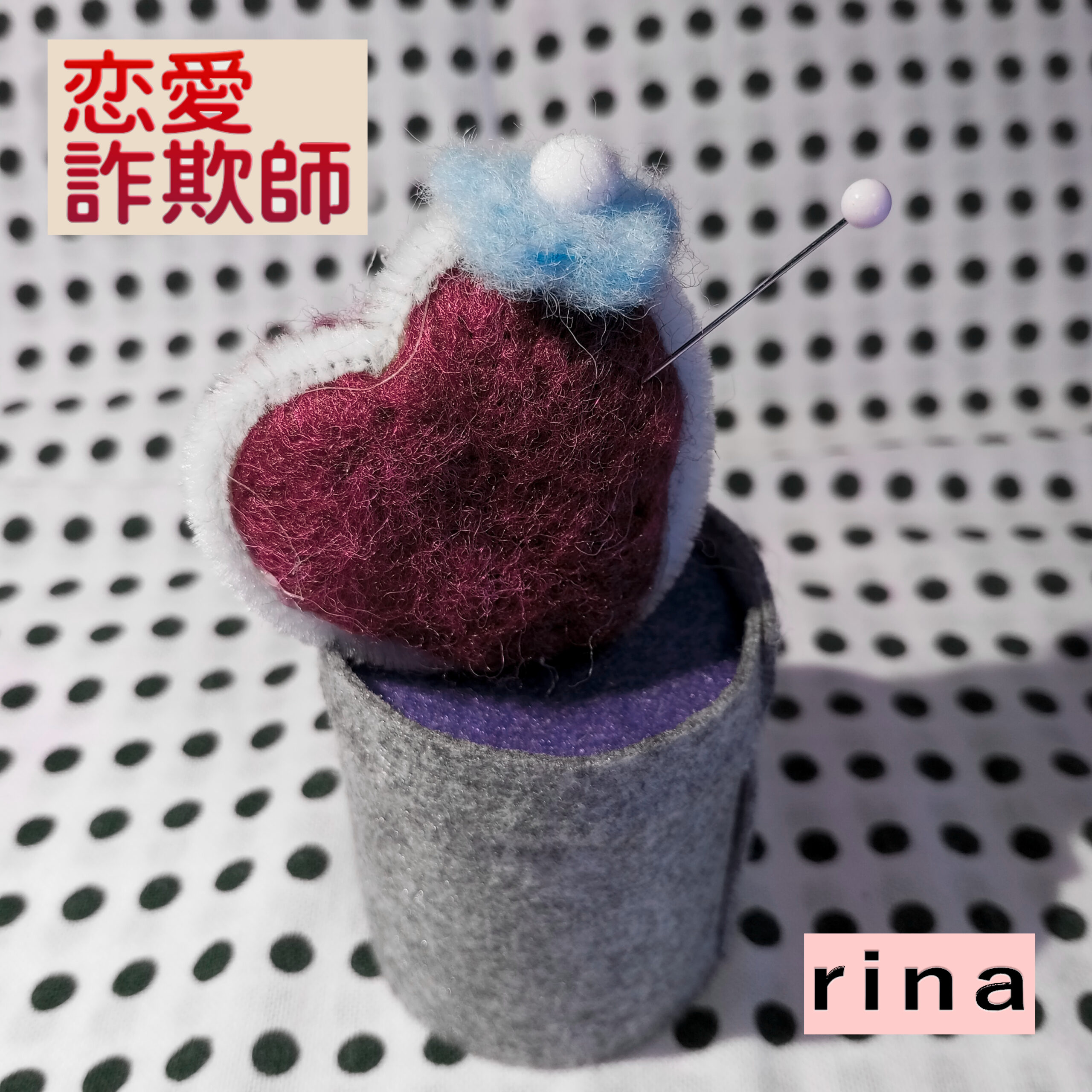1980年発表の、ザ・バグルス「ラジオスターの悲劇」(Video Killed the Radio Star)という曲があります。僕ら世代あたりの諸氏は全員ご存知でしょう。日本でも世界でも大ヒット、シンセや女性コーラスを取り入れたポップなサウンドと、ラジオボイス加工のトレヴァー・ホーンのボーカルも印象的な、メロディアスな楽しい曲です。
(イギリスでは1位だったが、アメリカは40位だったそうで意外)
この曲は、実はミュージックビデオ番組「MTV」が初めて流した曲だった……という話を、前回書いた映画「素晴らしき映画音楽たち」で知りました。皮肉というか、なんともアイコニックな出来事だったんですね。
なぜか自分の反応は「うわーっ」だったんですね(w)。意外すぎるというかなんというか……。映画でそのシーンが流れていましたが、今と違ってスリムな青年で、言われなきゃ絶対わからない。(現状随分貫禄付いちゃったから…)
それでも嘘かもしれないと思って、Youtubeで「ラジオスターの悲劇」のクリップを見たら、確かにそのシーンありました。コメント欄でジマー出演を書いている人がいて、やっぱり悲鳴が上がっている(w)。なんだろこれ、別に黒歴史じゃないはずだけどね、むしろ超有名曲だから栄誉…。
映画の中でこのことをバクロしてた業界のオジサンも、あの人昔こんなことしてたんだぜーみたいな、半笑いでコメントしてたから、やっぱり海外でも意外で面白いと思われているんでしょう。いやー人に歴史あり、それにしてもよりによってラジオスターの悲劇とは、なんとも強運をお持ちですね。
この曲からすっかり売れっ子になったトレヴァー・ホーンも現役らしく、最近のライブがYoutubeでたくさん出てきます。80年代のアーティストがまだ頑張っているのは僕らも心強い限りです。(この人はプロデューサーとしての活躍の方がデカいようです)
4/13終日、サーバー会社ネットオウルのトラブルでブログが閲覧不能でした。
砂塵舞うシティストリートに、流れる想いは…。
作詞・作編曲・プロデュース:弦央昭良
VIDEO
#シティポップ #エレクトロニカ #JPOP
◆4/12配信予定の新曲です。 「リベールシティ / まいみぃ」
砂塵舞うシティストリートに、流れる想いは…。
作詞・作編曲・プロデュース:弦央昭良
#シティポップ #エレクトロニカ #JPOP
それはきっと、失いたくない君の物語――。rinaのラブバラード
作詞・作編曲・プロデュース:弦央昭良
VIDEO
#AOR #バラード #エレクトロニカ #rina
◆3/18配信予定の新曲です。「恋愛詐欺師 / rina」
それはきっと、失いたくない君の物語――。rinaのラブバラード。
作詞・作編曲・プロデュース:弦央昭良
#J-POP #バラード #エレクトロニカ #rina
世界はキミと踊りたい。最先端・日本のシティポップ!
「街色シンパシィ / 棗 (from MistoriA)」
作詞・作編曲・プロデュース:弦央昭良
VIDEO
#CITYPOP #AOR #JPOP #EDM #エレクトロニカ #シンセポップ
◆2/15 配信予定の新曲です。「街色シンパシィ / 棗 (from MistoriA)」 世界はキミと踊りたい。最先端・日本のシティポップ!
#CITYPOP #JPOP #AOR #NatsumeFromMistoriA #エレクトロニカ #EDM
リアルタイムでは見られなかったが、NHKプラスで紅白歌合戦見ました。一応完走したが、ダンス主体と思われるアイドルグループは全部早送りです、スマン。
まずYOASOBI、満を持しての「アイドル」披露だったが、あの演出はちょっと……。ほぼ“バックダンサー”の皆さんしか映ってない。NHKは正に無能な働き者ですな。まあ口バク・当てぶりなんだけど、それでもみんなYOASOBIの雄姿を楽しみにしてたはず。
寺尾聰さんの「ルビーの指環」、バックバンド最高でしたね。イントロで演奏のあまりのカッコよさに悶絶。もちろん歌もそれに増して素晴らしかった。この曲が売れていた80年代の世界は、ほんと音楽好きにとっては楽園でした。寺尾さんは、横に置いたミキサーのフェーダーをご自分で動かされてましたね。(イヤモニ用?) ご存知ない方へ、この曲こそが「AOR」といわれるジャンルの代表曲です。
Official髭男dism、不勉強で知らなかったが、今年の歌コンの課題曲をやっていたんですね。ドラマチックでメロディラインの美しい、ちょっとトリッキーさもある良曲でございました。バーチャル合唱コラボも面白かった。
伊藤蘭さんのキャンディーズメドレー、これまたバックバンドの音に仰天。正に70年代の歌謡曲バンドの音を再現しています。ちょっと他では聞かれない音、コーラス2人とあわせてキャンディーズを再現、楽しかったです。
石川さゆりさんは、ウクライナの民族楽器とデュオでの「津軽海峡・冬景色」で不思議な世界を魅せてくれました。演歌は、実は日本の民族音楽=民謡のDNAも入ってるから、こういう異色コラボも意外と合うんですね。
そして忘れちゃいけないクイーン(+アダム・ランバート)。流石の貫禄で、エッジ効きまくりのロックサウンドを聞かせてくれました。ブライアン・メイのギターのワイルドさは当時より進化してるかも。ロジャー・テイラーのドラムは、ちょっとPAが良くなかったようで平坦に聞こえた、そこだけは残念。
ディズニーメドレーの女性司会者二人の歌。ネット記事になりまくってましたが、自分も心の準備をして臨んだものの、パソコンの前で冒頭から爆笑してました(ゴメン)。画面の豪華絢爛さと、歌声の微妙さのギャップが凄い。でもきっと、初めての紅白歌唱で緊張したんですね。次回リベンジ期待。ここに、期待を込めて個人的MVPを贈りたいと思います。
追記
VIDEO 声:音読さん
誰かと誰かは微妙な関係…EDM POP!
「イチャ・チャ / rina」
#EDM #JPOP #シンセポップ #rina
誰かと誰かは微妙な関係… EDM POP!
Release Date:2023/12/04